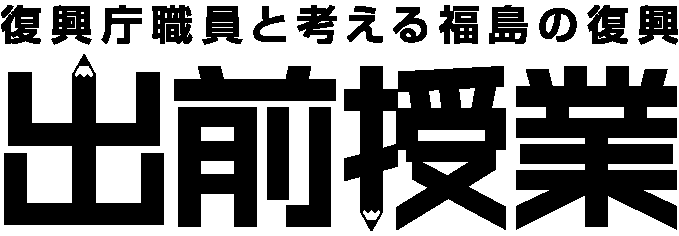【東日本大震災からの復興】
最初に東日本大震災の被害やその後の復興について解説がありました。震災から10年以上がたち、大きな被害を受けた町にも新しい駅ができるなど生活が戻ってきています。一方で、東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示が出された市町村の中で、まだ住民が戻れていないところもあることに、生徒からは「初めて知った」という声が上がりました。

【原子力発電所の廃炉に向けた取り組み】
震災復興には、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みが必要不可欠です。講義では廃炉についての説明動画を視聴した後、その必要性について土田さんが説明しました。
地震と津波で電力を喪失し、水素爆発を起こした原子炉内には溶けて固まった「燃料デブリ」があります。継続的に注水することで安定状態を保っていますが、冷却水は放射性物質に汚染されます。こうした水から多核種除去設備(ALPS)によって放射性物質のほとんどを取り除いた処理水(「ALPS処理水」)がタンクに保管されています。廃炉を進めるため、国は2021年、ALPS処理水を海に放出する方針を決定しました。海洋放出は国際原子力機関(IAEA)から実現可能であると評価されており、放出にあたってはモニタリングが行われるなど、国際社会の監視下で進められる予定です。

【風評影響について】
震災復興に向けたもう一つの課題として、風評被害があります。震災発生当初に「福島県産の農林水産物を食べてはいけない」といった形で広まったうわさ。国や福島県は、農林水産物の出荷前のモニタリング検査の実施や、放射性物質が基準値を超えるものを流通させないなど、徹底的に検査を行う体制を確立しました。こうした取り組みによって、当初は輸入規制していた諸外国の多くが規制措置を撤廃するなど、影響は少しずつ緩和されています。
それでも米や牛肉などの出荷量は震災前の水準に回復しておらず、農林水産物の一部の価格は今も全国平均を下回っています。
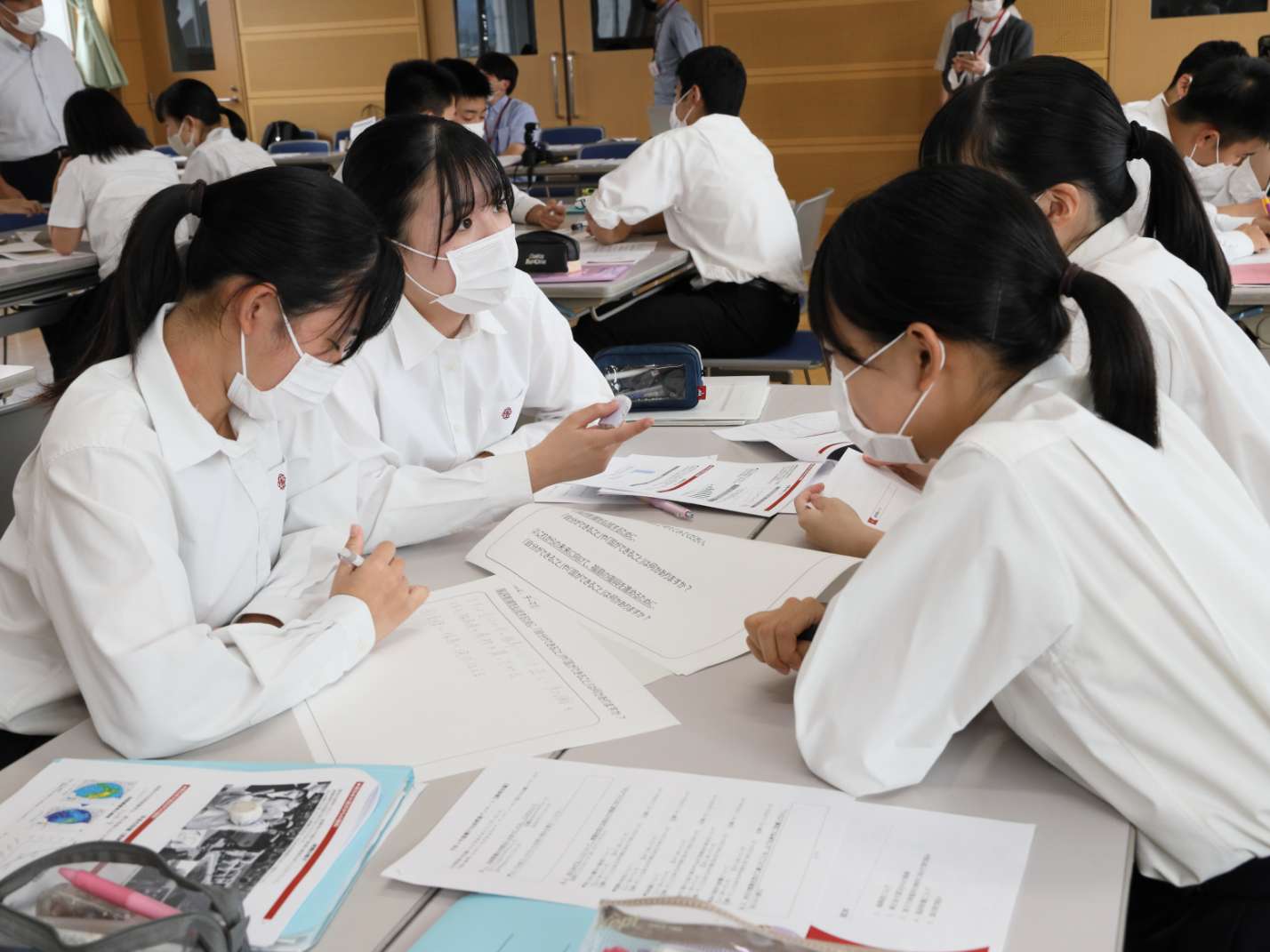
【風評の影響を払拭し、福島の復興を進めるには】
福島の現状や課題を聞いた後、ワークショップを行いました。生徒たちは3~4人のグループごとに「風評被害を払拭するためにできること」「未来に向けて復興を進めるためにできること」をテーマに活発に意見交換しました。発表では「実際に福島に行って現状を見てみたい」「インフルエンサーにSNSや動画などで発信してもらう」「スポーツの全国大会を福島で開催する」など柔軟な発想の意見が飛び出しました。
その後、土田さんは国の取り組みを説明。福島の情報を発信するラジオ番組やYouTube動画、福島の農林水産物を食べてもらうためのイベントを各地で開催していること、福島に新たな産業を呼び込む「イノベーション・コースト構想」が進められていることなどを話しました。そして「ご家族や友人に話すという小さな一歩が復興への取り組みにつながる。ぜひ話題にしてほしい」と締めくくりました。