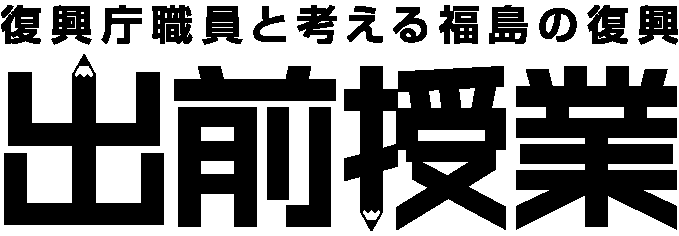【東日本大震災からの復興】
2011年3月11日、地震や津波に加え、原子力発電所事故も発生する複合災害で深刻な被害が出ました。ピーク時で約16万5千人に上った福島県の避難者の多くは自宅に戻りましたが、今も約3万4千人の方が戻れずにいます。もう全員帰還したと思っていた生徒もおり、驚いた様子でした。一方で、かつて除染廃棄物を入れた袋が山積みになっていた仮置場が水田に戻るなど、復興が進む写真に見入る場面もありました。

【原子力発電所の廃炉に向けた取り組み】
津波などの影響で電源を失い、燃料の冷却ができなくなった福島第1原子力発電所では、水素爆発により、大気中に放射性物質が飛散しました。今も強い放射線を発する、溶けて固まった核燃料などを除去し、施設を安全に解体·撤去するのが廃炉です。廃炉の作業は今後長期にわたりますが、雨や地下水の流入で、放射性物質に汚染された水が発生し続けています。放射性物質のほとんどは多核種除去設備(ALPS)で取り除けますが、トリチウムだけは困難です。「129万トンの処理水をためた千基以上のタンクが廃炉の障害になっており、処理水の処分は復興に不可欠」との説明を受けるとともに、処分の安全性について「トリチウムは雨や水道水にも含まれており、体内に取り込んでも蓄積されずに排出される。国は、トリチウム以外の放射性物資を徹底的に取り除いた上で、安心のため、トリチウムを含むALPS処理水は大幅に薄めて海に流すことを決めた」との説明もありました。

【風評影響について】
中見参事官は現在では世界各地の放射線量と福島県内の放射線量がほぼ同水準であることを示しました。
また広まっている風評として、福島県内では放射線の影響でがん患者が増えた▽震災当時に受けた放射線による影響が今後生まれてくる子どもに遺伝する▽スーパーで売られている福島産の農林水産物を食べると放射線により健康に影響が出る―などの例を挙げ、科学的根拠がない誤解だと否定しました。お米やモモ、魚など農林水産物は厳しいモニタリング検査を受け、基準を超えるものはスーパーなどには並ばず、今では基準超過自体がほぼなくなっています。ただ、中見参事官は、「本来安全であるはずのALPS 処理水の海洋放出によって、水産物への風評が再び起こらないかを心配する声もある」と述べました。

【風評の影響を払拭し、福島の復興を進めるには】
生徒は班ごとに分かれ、「自分ができること」、「国ができること」は何かを話し合いました。「もし、自分の作った作物が風評のせいで売れなかったら、悲しい」という声も聞かれました。また、交流サイト(SNS)で情報発信を行うべきとの意見が多く出ました。中見参事官は、国は動画投稿サイト「Youtube」の配信などを行っているが、「なかなか見てもらえない難しさがある」と言います。また、ITやロボットを使った大規模農業の実証実験や、水素をはじめとする新エネルギー研究などに取り組む「イノベーション·コースト構想」も一つの答えと語りました。最後に「震災を機に生まれた復興庁が、11年かけていまだ解決できてない、正解のない難しい問題を一緒に考えてもらった。これからも関心を持ち続け、家族や友達と話してみてほしい」と呼び掛けました。