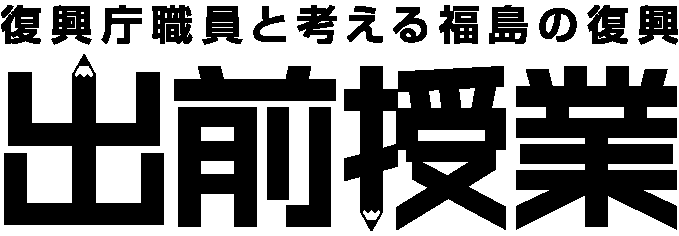【東日本大震災からの復興】
2011年3月11日に発生した東日本大震災を受け、復興の道のりにある福島の現状と、東京電力福島第一原子力発電所で進んでいる廃炉に向けた取り組み、来春に控えているALPS処理水の海洋放出などについて学んだ後、生徒たちは「今自分たちにできること」を考えました。
徳増さんは、東日本大震災では大きな津波に襲われただけでなく、原子力発電所が水素爆発を起こし周囲に放射性物質が飛散したこと、の二つの災害が起きたことをまず述べました。
原発事故の災害に見舞われた福島県内の復興状況については、放射線量は県内の大半の地域では大幅に低下し、避難者数がピーク時の16万5千人から3万4千人に減っています。一方で、産業の状況を見ると、避難地域12市町村では製造品出荷額が震災前に比べ8割程度まで戻っているものの、営農再開面積は38%、沿岸漁業の水揚量は18%と、特に農林水産業の影響が長期化していることを課題として挙げました。

【原子力発電所の廃炉に向けた取り組み】
地震と津波の影響により原子力発電所は電力を喪失し、原子炉に送水できなくなった結果、燃料が発熱し、水素爆発が起きました。現在は廃炉に向け、溶けた燃料などが冷えて固まった燃料デブリを取り出す作業を進めていこうとしていますが、雨水や地下水の流入などにより汚染された水(汚染水)が大量に発生し続けている現状を説明しました。
こうした水は多核種除去設備(ALPS)により、トリチウム以外の放射性物質を規制基準値以下まで浄化し、「ALPS処理水」として敷地内のタンクに貯められます。敷地にはすでに1千tの容量を持つタンクが1千個以上あり、廃炉作業に必要なスペースを確保するためにはこのまま増やし続けることができない状況です。そこで国はトリチウムを含むALPS処理水を海水で薄めて、海に流す海洋放出を決めています。

【風評影響について】
福島県は県内で収穫された農林水産物について放射性物質が含まれていないかどうかのモニタリング検査などを行い、結果を公表しています。近年は基準値を超えるものはほとんどなく、国際機関もこうした取り組みが機能していると評価しています。ただ、コメ、牛肉など重点6品目の出荷量は震災前の水準までは回復しておらず、諸外国・地域の輸入規制も減りつつあるものの、今も香港、中国、台湾、韓国、マカオ等の規制は続いています。また、外国人の延べ宿泊者数も伸び率が全国に比べて低調であることなど、風評影響が残っていることに触れました。
授業の最中は、生徒が熱心にメモを取る様子が見られ、生徒からALPS処理水の海洋放出後の風評被害の懸念について質問があるなど、テーマへの関心の高さがうかがえました。授業の後、生徒たちは20のグループに分かれ、風評被害を払しょくするためにできること、福島の復興に向けてできること、の2つのテーマでグループワークを行い、「自分たちで福島産のものを食べ、感想をSNSであげる」などの意見が出されました。