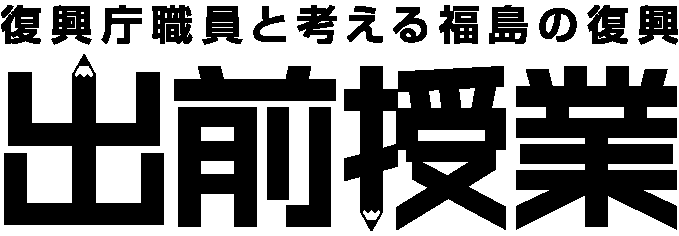【東日本大震災からの復興】
東日本大震災は、地震と津波、原子力発電所の事故が重なった世界でも例のない災害で、死者·行方不明者合わせて約2万2千人に上っています。
原発事故が起きた福島県では、約16.5万人が避難生活を強いられました。現在は放射線量が大幅に低下し、避難指示区域の面積は5分の1にまで減少し、県内の2.4%となっています。しかし、いまだに3万人近くが避難生活を続けており、残る地域についても「一日も早く避難指示の解除に努めたい」と話しました。

【原子力発電所の廃炉に向けた取り組み】
事故を起こした福島第1原子力発電所の廃炉は、復興への大前提。廃炉には30年以上かかるといわれています。長い工程の中でまず課題となったのは、原子炉を冷やした水をどう取り扱うかという問題。これまではこうした放射性物質を含む汚染水を多核種除去設備(ALPS)によって処理し、規制の基準以下にしたALPS処理水を原発敷地内のタンクにためてきました。しかし、その量は129万トンにまで増え、これ以上、タンクを増やせない状況になっています。
国は2021年、このALPS処理水を海洋放出する方針を決めました。海洋放出は、国際原子力機関(IAEA)と連携しながら、国際社会の監視の下で行われます。廃炉に向けては、核燃料が溶けて冷え固まった「燃料デブリ」を原子炉内から取り出す作業があります。ロボットを遠隔操作して進めるなど最先端の技術を駆使し、環境リスクを回避しながら進められます。

【風評影響について】
復興を妨げる課題の一つとして、風評被害があり、福島の特産物であるお米や牛肉、桃などの出荷量は、震災前の水準に戻っていません。消費者の福島県産食品に関する不安は減少しているものの、小売や卸売業者が取り扱いを抑制し、最終的に生産者が作ること自体をためらう悪循環が起きていると復興庁は分析しています。
この影響は、国内にとどまりません。原発事故後、55の国や地域が被災地の産品の輸入を規制しました。このうち43カ国·地域は規制措置を撤廃しましたが、今なお12の国と地域では規制が継続しています。また、海外からの福島への観光客も伸び悩んでいます。
世界各国の公的機関が公表した主要都市の放射線量と福島県の放射線量は現在、ほぼ同水準。外国の生徒も出席した講義では「科学的なデータを示しながら理解を求めていきたい」と強調しました。

【風評の影響を払拭し、福島の復興を進めるには】
生徒は班に分かれワークショップに臨み、風評払拭やこれからの未来のために「自分ができること」「国ができること」について話し合いました。「実際に被災地に出かけ、見て考えることが大事だ」「福島県の農水産物を消費し、交流サイト(SNS)を通じて、世界に安全性を発信したい」等の意見が発表されました。
被災地を元気づけるために①知ってもらう②食べてもらう③来てもらう、の3本柱で取り組んでいます。①ラジオ媒体やYoutube 等を活用した情報発信やパンフレットの作成をしています。②と③については「九州から少し遠いけど、現地で味わうことにより、イメージは大きく変わる」と徳増参事官。移住や定住を進めるための施策や、水素エネルギーやロボットなどの産業を集積させる構想も紹介し「これからも被災地に寄り添っていきたい」と述べました。