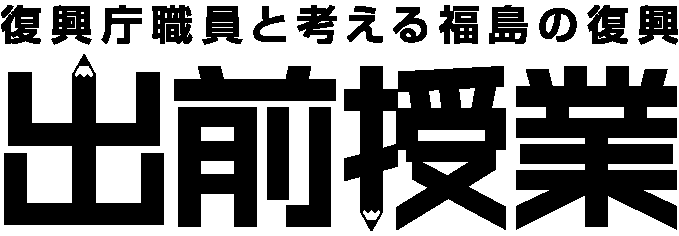【東日本大震災からの復興】
まずは当時の状況を振り返ろうと、震災や東京電力福島第1原子力発電所(原発)事故の発生と経緯に触れました。復興の状況として、空気中の放射線量を表す「空間線量率」が、原発事故の影響がないエリアと同水準程度まで低下▽多くの地域で避難指示が解除▽インフラの整備が進行―などを紹介しました。一方で3万人以上がいまだに避難生活を続けていることや、風評被害によって回復が遅れている産業があることも課題として挙げました。

【原子力発電所の廃炉に向けた取り組み】
国は「復興と廃炉の両立」という原則の下に指針を掲げ、それに沿った取り組みを進めています。廃炉の実現には、核燃料や原子炉内の構造物と燃料が溶けて固まった燃料デブリの取り出し、燃料デブリを冷却した汚染水の処分、施設の解体といった作業が必要です。今回の授業では、ALPS処理水の処分を取り上げ、その工程などを映像で紹介しました。
汚染水は、多核種除去設備(ALPS)でトリチウム以外の放射性物質を取り除いて浄化処理されます。処理された水は「ALPS処理水」と呼ばれ、今も増え続けており、2023年春以降にALPS 処理水の海洋放出を始めると説明しました。海洋放出にあたって、国際原子力機関(IAEA)による検証が行われたことも紹介。生徒たちは動画を食い入るように見つめ、真剣にメモを取っていました。

【風評影響について】
「福島県産の食品は発がんリスクが高いから買わない」。こうした風評は11年たった今でも一部に残っています。震災後に下落した農作物の価格の一部は回復しておらず、米や牛肉などの出荷量も震災前の水準には戻っていません。海外に目を向けると、中国や韓国など5カ国が輸入を停止していることや外国人観光客の伸び率が低調という事実も紹介しました。「正確な情報を広く伝えていくことが私たちの役割です」と土田さんは力を込めました。

【風評の影響を払拭し、福島の復興を進めるには】
同校では秋休みの期間を使って、東日本大震災のことを調べる事前学習を実施。その中で「復興に向けた国の取り組みで大事にしていることは何か」「具体的にどう行動すればいいのか」といった疑問を持ち寄り、土田さんに質問する一幕もありました。
その後、「復興のために自分ができること、国ができること」をテーマにしたグループディスカッションを行いました。発表では、「事前学習でALPS処理水を海洋放出することを知った。国内外の機関で検証され、安全だと分かった」「町の復興が進む一方で避難した人が戻り切れていないことを知った」といった声のほか、風評の影響の払拭に向けて「福島県産の商品をPRする機会を増やす」などの意見も挙がりました。
「知ってもらい、買ってもらい、来てもらうことが福島の復興につながります。まずは今日学んだことを家族や友人に伝えてください。それが復興支援の第一歩になります」と土田さんは授業を締めくくりました。生徒たちにとって、広島から遠く離れた場所で起きた災害を自分事に感じる、いい機会となりました。