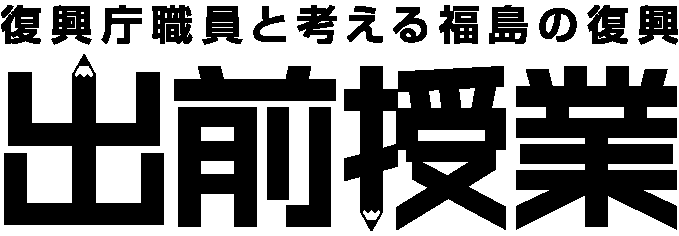【東日本大震災からの復興】
はじめに、震災の発生と東京電力福島第一原子力発電所(以下原発)の事故発生の経緯について触れました。放射線量は震災直後から大幅に低下し人体への影響がないことや、多くの地域で避難指示が解除され、インフラが整備されるなど、復興が進む一方で、原発事故の影響で回復が遅れている産業があることや未だに帰還できない地域があり、避難が続いている人がいるといった課題も紹介されました。

【原子力発電所の廃炉に向けた取り組み】
次に取り上げたのが、今も続く原発の廃炉に向けた取り組みです。廃炉とは必要のなくなった原子炉や関連設備を解体·処分すること。その工程の一つである「ALPS処理水の処分」について、映像を交えながら説明しました。雨水や地下水が流入することなどで放射性物質に汚染された水が発生し続けています。こうした水は、浄化処理が必要となり、ALPSという設備により、トリチウムを除く放射性物質を規制基準以下まで除去し、敷地内のタンクで一時保管されることになります。このALPS処理水について、タンクを増やし続けるにも限界があり、国際的な監視のもとで海洋へ放出することが予定されていること、ALPS処理水に含まれるトリチウムは、放射線が微弱で、体内に入っても蓄積されないなど、健康への心配はないことなどを解説しました。中見さんは「復興に向けて廃炉は不可欠。そのためにしっかりと安全性を確保してALPS処理水の処分を行っていきます」と話し、重要性を伝えました。学生たちは真剣にメモをとり、興味深く話を聞いていました。

【風評影響について】
もう一つの課題が風評被害。震災後「売っている福島県産の農林水産物を食べるとがんのリスクが増える」など根拠に基づかない噂が立ち、社会問題になりました。震災から10年以上経った今でも、こうした風評によって、農林水産物の出荷や輸出、観光業について深刻な影響が残っていることが紹介されました。

【風評の影響を払拭し、福島の復興を進めるには】
説明に対して、復興が実現し支援が必要なくなるのはいつか、除染による廃棄物の最終処分はどうする予定かなど、生徒から多くの真剣な質問が寄せられました。
その後、班ごとのグループディスカッションが行われ、復興のために自分ができることと国ができることについて、活発に意見を交換し、発表しました。「さまざまな問題を自分ごととして捉え、考え続けるべき」「ネットの情報に惑わされず、正しい知識を持つことが大切」といった発言や「SNSを活用して情報発信すべき」「教育の場でももっと復興のことをとりあげるべき」といった意見がありました。
最後に、中見さんは「今日知った情報や被災地の現状を身近な人に伝えてください。それが復興支援につながります」と話しました。今回の出前授業は、生徒それぞれが被災地の問題に対して何ができるかを考える機会となりました。